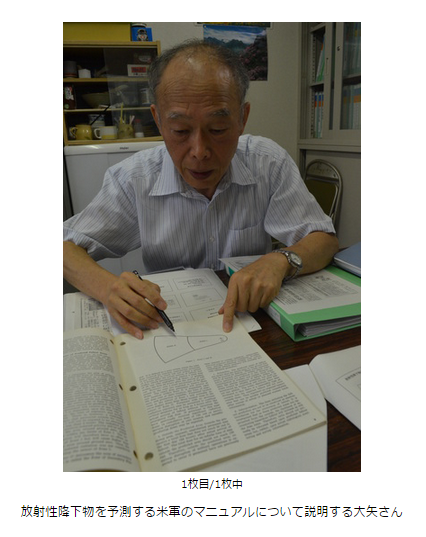米軍資料で原爆被害解析 /長崎
毎日新聞 2014年09月09日 地方版
長崎総合科学大の大矢正人名誉教授(67)が、長崎原爆投下時に米軍が撮影したきのこ雲の映像や、戦場で核兵器が使用された際に米兵が放射性降下物を予測するためのマニュアルなどを基に、長崎原爆の被害の解明を試みている。大矢さんは「今の時点で我々が持つ疑問について、1次資料を入手して今の科学的知見を活用して解明することが重要だ。それを次世代に残すことが継承につながる」と語る。
大矢さんは神戸市出身。大阪大工学部、同大大学院で応用物理を学び、1974年に長崎造船大(現長崎総合科学大)の講師になった。総科大教授だった故・鎌田定夫さんとの交流を通して原爆問題に関心を持ち、同大の長崎平和文化研究所長などを務めた。現在は、原水爆禁止県協議会の代表理事を務める。
きのこ雲の映像は長崎上空から爆撃機が撮影したもので約8分。米スタンフォード大フーバー研究所から入手した。原爆のさく裂できのこ雲が発生し、時間の経過とともに白い「傘」の部分と黒い「柄」の部分が分離していく様子などが記録されている。
映像からきのこ雲の下に発生した土煙の広がりや、雲の高さなどを解析。また、映像と、衛星写真を地球儀を回すように見ることができるソフト「グーグルアース」の画像を海岸線の地形などを基に重ね合わせ、撮影した爆撃機の高度や位置を分析している。
これとは別に、戦場で核兵器が地表爆発した際に兵士が放射性降下物で被ばくする恐れがある範囲を予測するための米軍のマニュアル(73年)を入手。風力と爆発力から簡易予測できるとされ、長崎原爆のデータをあてはめると、放射性降下物によって1・5シーベルトの被ばくをする恐れがある範囲は、爆心から東方向には16キロにも及ぶことが分かった。
マニュアルは地表爆発を想定しており、地上約500メートルでさく裂したとされる長崎原爆にはそのまま当てはめられないが、いまだ未解明の原爆の放射性降下物の影響を知るうえで、米国が作成した資料は興味深い。
この他、大矢さんは、45年12月〜46年1月に理化学研究所グループが長崎市周辺や島原半島などで測定した残留放射線の測定データの解析などを進めている。大矢さんは「米軍は当初、原爆の放射性降下物の影響はないと述べていたが、長崎の西山地区では実際に高い線量が測定されている。影響を解明するには、残された映像や測定値、体験した人の証言などが重要な役割を果たす」と指摘する。
【樋口岳大】
理研の放射線記録入手 /長崎
毎日新聞 2015年04月09日 地方版
長崎原爆の投下から間もない1945年12月〜46年1月に、理化学研究所のグループが長崎市や島原半島で残留放射線を測定した詳細な記録を、大矢正人・長崎総合科学大名誉教授(68)が入手した。測定した全域について、地図上に約100地点の線量率や測定地点、測定日などが手書きで記録されている。長崎では国の指定地域外で原爆に遭った「被爆体験者」が被ばくによる健康被害の可能性を主張して被爆者と認めるよう訴えているが、大矢氏は「入手した資料により、被爆体験者の区域を含め広範囲の放射線の影響をより詳しく知ることができる」と語る。
原爆投下から4カ月余り後の45年12月25日〜46年1月22日、理研グループの研究者3人が長崎原爆の残留放射線を測定。大まかな測定結果を記した概略図は53年に日本学術会議が発行した「原子爆弾災害調査報告集」に掲載された。その後も測定に参加した一人である故中根良平氏の報告に爆心地や比較的線量が高かった長崎市西山地区など一部地区について詳細な測定図が掲載されたことがあった。しかし、爆心地から約7キロ以遠の被爆体験者の区域を含む地域については、詳しい測定地点や測定日などのデータは知られていなかった。
今回、大矢氏が入手した記録は、測定に参加した研究者の故坂田民雄氏が長年保管し、死後は理研に保管されていた。爆心地や西山地区のほか、被爆体験者の区域を含む長崎市東部や島原半島などで、地図上に測定地点の印が付けられて線量率や測定日などが記されている。「郵便局横」や「岩田屋玄関」など詳しい説明が書き込まれた測定地点もあった。
記録によると、被爆体験者の区域である爆心地の東約8キロの長崎市矢上地区では、45年12月29日に測定された放射線量率は自然放射線の14・7倍で、大矢氏は原爆投下から1年間の被ばく線量を73ミリシーベルトと推定した。東京電力福島第1原発事故で国が避難の目安としている年20ミリシーベルトを上回った。また、同約48キロの島原市では線量率が比較的高く46年1月11日の測定で線量率は自然放射線の3・3倍、1年間の推定被ばく線量は14ミリシーベルトと試算した。
大矢氏は「被爆者援護は原爆被害の実相に基づいて考えるべきだ。記録は、実相に近づくための客観的資料の一つになる」と語った。
【樋口岳大】